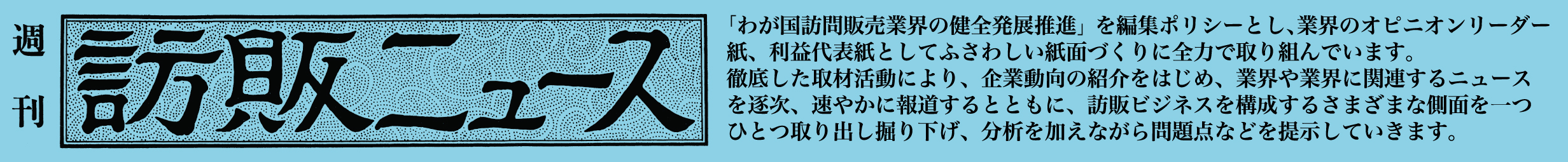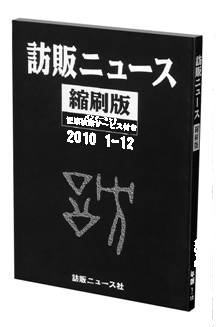社説 対岸の火事ではない
本紙3月6日号で既報のように、ダイレクトセリング化粧品最大手のポーラの業績が振るわない。コロナ禍前をピークに売上は伸び悩んでおり、直近の2024年12月期を含んで3期連続の1000億円割れとなった(ビューティケア事業・ポーラブランド売上)。2000年以降、鈴木郷史氏(現・ポーラ・オルビスホールディングス代表取締役会長)の下で大鉈を振るい、〝昭和の化粧品ブランド〟からの脱却に成功したポーラが、いま再び苦境に陥っている。しかし、これは他のダイレクトセリング化粧品にとっても決して対岸の火事ではない。
売上不振の対策として、ポーラが主に行っている施策は、リアル店舗とECなど他チャネルとの連動、それによる新しいユーザー層の開拓だ。特にECチャネルは、主力の委託販売に比べればその売上は微々たるものだが、従来型チャネルに比べて顧客層が若く、またブランドに求める価値もベクトルが異なっている。委託販売チャネルは、主力販売員の高齢化に伴う営業力の低下が明らかで、テコ入れをしても縮小を避けられない。であれば、ブランドのリソースを将来的に成長の可能性があるカテゴリーに振り分けていくというのは、経営方針としては理に適っている。そのための、小林琢磨新社長の就任であることは言うまでもない。
ポーラは、自身のブランドの価値を高め、高機能・高付加価値・高価格のハイブランドとすることで、旧来のイメージからの脱却を図ってきた。この施策は、主にリーマンショック以降に積極的に進められてきた。〝失われた30年〟と言われる経済状況の中でも、最高峰ブランド「B.A」やシワ改善ブランド「リンクルショット」などのヒットシリーズを生み出して、ポーラがリーディングカンパニーとしての立ち位置を確固たるものにしてきたのは事実。今後、このハイブランド戦略は変更されることなく、さらに推進していく方向だが、以前とは状況が異なる。あらゆるものの値段が上がり、負担感が増していく中、ハイブランドのユーザー層にフォーカスしたいのはポーラだけではない。化粧品市場では購買層の二極化が顕著で、ダイレクトセリング化粧品企業の多くは、高価格帯を愛用する層に的を絞ることでブランドの存続を図ろうとしている。しかし、経済状況は政府が言うほど好転していないのが実情であり、ハイブランドのユーザー層でも、機能性とコスパに優れた化粧品にスイッチする向きもある。
ポーラの戦略は、ダイレクトセリング化粧品各社が内包する課題を踏まえつつ、かつ正攻法で突破を試みるという側面をもつ。この取り組みの成否如何では、各社も今後の戦略の見直しを迫られることになるのではないか。コロナ禍が収束したとはいえ、未だ楽観視できない状況が続いている。
売上不振の対策として、ポーラが主に行っている施策は、リアル店舗とECなど他チャネルとの連動、それによる新しいユーザー層の開拓だ。特にECチャネルは、主力の委託販売に比べればその売上は微々たるものだが、従来型チャネルに比べて顧客層が若く、またブランドに求める価値もベクトルが異なっている。委託販売チャネルは、主力販売員の高齢化に伴う営業力の低下が明らかで、テコ入れをしても縮小を避けられない。であれば、ブランドのリソースを将来的に成長の可能性があるカテゴリーに振り分けていくというのは、経営方針としては理に適っている。そのための、小林琢磨新社長の就任であることは言うまでもない。
ポーラは、自身のブランドの価値を高め、高機能・高付加価値・高価格のハイブランドとすることで、旧来のイメージからの脱却を図ってきた。この施策は、主にリーマンショック以降に積極的に進められてきた。〝失われた30年〟と言われる経済状況の中でも、最高峰ブランド「B.A」やシワ改善ブランド「リンクルショット」などのヒットシリーズを生み出して、ポーラがリーディングカンパニーとしての立ち位置を確固たるものにしてきたのは事実。今後、このハイブランド戦略は変更されることなく、さらに推進していく方向だが、以前とは状況が異なる。あらゆるものの値段が上がり、負担感が増していく中、ハイブランドのユーザー層にフォーカスしたいのはポーラだけではない。化粧品市場では購買層の二極化が顕著で、ダイレクトセリング化粧品企業の多くは、高価格帯を愛用する層に的を絞ることでブランドの存続を図ろうとしている。しかし、経済状況は政府が言うほど好転していないのが実情であり、ハイブランドのユーザー層でも、機能性とコスパに優れた化粧品にスイッチする向きもある。
ポーラの戦略は、ダイレクトセリング化粧品各社が内包する課題を踏まえつつ、かつ正攻法で突破を試みるという側面をもつ。この取り組みの成否如何では、各社も今後の戦略の見直しを迫られることになるのではないか。コロナ禍が収束したとはいえ、未だ楽観視できない状況が続いている。