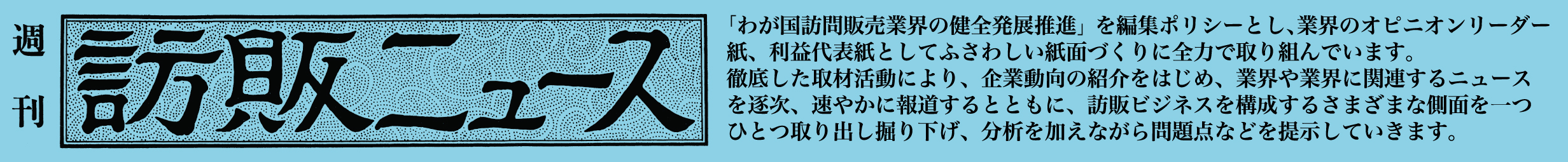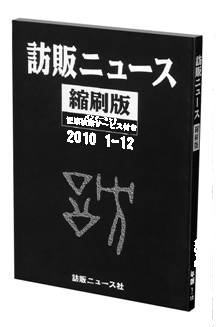社説 電子化実態調査 特役の〝特例〟扱い、ワケは
消費者庁の実態調査で、特定商取引法の「書面電子化」制度を利用している事業者はほとんどいないとされていたことが分かった。理由は複雑かつ煩雑な手続きと、それに伴う法リスクの高さ。模擬サイト上で電磁的交付の手続きを消費者に体験してもらう調査でも、制度に起因するユーザビリティの低さが露わになった。電子化を可能とした改正法は「施行2年後見直し」規定をもち、来年6月に到来する。見直しが始まれば、調査報告の内容は検討の際、基本資料として活用され得る。
ところで、事業者が対象の調査で、このような実態を掴めない可能性があったことは、指摘しておかざるを得ない。当初は、特定継続的役務提供(以下特役)を実施し、かつ実際に書面電子化を行っている事業者のみを調査する予定だったからだ。
しかし、電子化が可能となった類型には、訪問販売など5類型が含まれる。また、すでに電子化を実施済みの事業者だけを調べたのでは、制度の実状に迫ることは難しい。委託事業が落札される前に、この点を本紙は指摘。その後、同庁は特役の”特例扱い”を転換。6類型すべてを対象に電子化を未実施の事業者を含むこととした。調査報告書は「より広範に取組状況を確認するために、消費者庁と協議のもと対象を拡大」したとしている。
消費者庁は特役のみ調査する理由に、訪問販売等は覆面形式の試買調査が難しい旨を説明していた。が、実際の調査では結局、試買調査を行えておらず、代わりにアンケートとヒアリングの対象を拡大している。調査対象を6類型すべてに広げていなければ対象の拡大は難しく、調査に投じた貴重な税金が宙に浮いた可能性さえある。
一方、消費者を対象とした調査では特役の”特例扱い”を維持。オンライン完結型の英会話学習と結婚相手紹介の2サービスで模擬サイトを用意し、疑似的購入体験の分析が行われた。模擬サイトにおける一連の手続きの流れを「黒塗り」して開示した消費者庁は、その理由を”電子化に関する消費者庁の公式見解であるかのような誤解を招く””模倣した事業者に法令に適合しない手続きを誘発させかねない”と説明した。
一利あるようにも聞こえるが、そもそも何故、「完全電子化」が可能な特役のみを対象にモデルケースとなり得るサイトを用意し、消費者の使い勝手を掴む必要があるのか。この調査には、事業者が対象の調査より400万円多い1100万円の税金が投じられた。
4年前、電子化の”出発点”となった規制改革推進会議で取り上げられた類型はオンライン英会話学習だった。今後も”特例扱い”が続くようなら、制度の歪みはさらに大きくなるのではないか。
ところで、事業者が対象の調査で、このような実態を掴めない可能性があったことは、指摘しておかざるを得ない。当初は、特定継続的役務提供(以下特役)を実施し、かつ実際に書面電子化を行っている事業者のみを調査する予定だったからだ。
しかし、電子化が可能となった類型には、訪問販売など5類型が含まれる。また、すでに電子化を実施済みの事業者だけを調べたのでは、制度の実状に迫ることは難しい。委託事業が落札される前に、この点を本紙は指摘。その後、同庁は特役の”特例扱い”を転換。6類型すべてを対象に電子化を未実施の事業者を含むこととした。調査報告書は「より広範に取組状況を確認するために、消費者庁と協議のもと対象を拡大」したとしている。
消費者庁は特役のみ調査する理由に、訪問販売等は覆面形式の試買調査が難しい旨を説明していた。が、実際の調査では結局、試買調査を行えておらず、代わりにアンケートとヒアリングの対象を拡大している。調査対象を6類型すべてに広げていなければ対象の拡大は難しく、調査に投じた貴重な税金が宙に浮いた可能性さえある。
一方、消費者を対象とした調査では特役の”特例扱い”を維持。オンライン完結型の英会話学習と結婚相手紹介の2サービスで模擬サイトを用意し、疑似的購入体験の分析が行われた。模擬サイトにおける一連の手続きの流れを「黒塗り」して開示した消費者庁は、その理由を”電子化に関する消費者庁の公式見解であるかのような誤解を招く””模倣した事業者に法令に適合しない手続きを誘発させかねない”と説明した。
一利あるようにも聞こえるが、そもそも何故、「完全電子化」が可能な特役のみを対象にモデルケースとなり得るサイトを用意し、消費者の使い勝手を掴む必要があるのか。この調査には、事業者が対象の調査より400万円多い1100万円の税金が投じられた。
4年前、電子化の”出発点”となった規制改革推進会議で取り上げられた類型はオンライン英会話学習だった。今後も”特例扱い”が続くようなら、制度の歪みはさらに大きくなるのではないか。