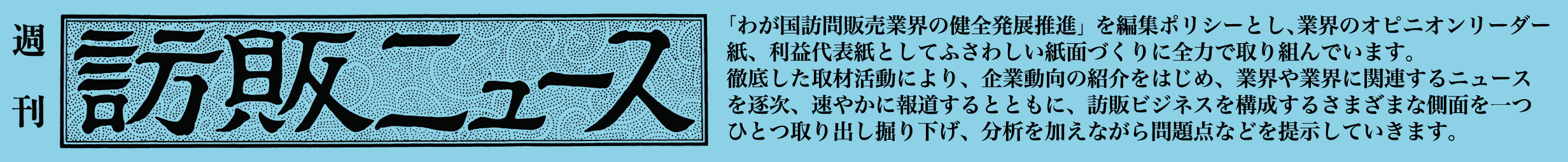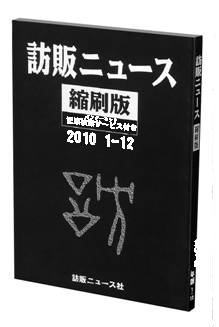消費者被害救済策、再検討の可能性は?
消費者庁の「研究会」、昨年より非公開で議論
3月末に報告書、今後の活用「現時点で白紙」
「ジャパンライフ」事件等に代表される、現行法で対応の難しい深刻な消費者被害を防ぎ、被害を救済するには、どのような手立てが有効なのか。昨年、消費者庁が有識者の「研究会」を設け、議論の中身が3月末までに取りまとめられる見通しだ。議論の主題の一つは、行政の裁判所に対する差止命令申立て制度。同庁の過去の有識者会議で提案されたものの〝棚ざらし〟状態にあったが、一昨年の自民党の政策提言に盛り込まれ、「研究会」のきっかけとなった。一方、「研究会」が委託事業で行われていることを理由に、議論の中身は非公開。取りまとめ結果の具体的活用は現時点で予定しないという。
裁判所への差止命令
申立て権など議題に
現在、金銭的被害の回復を目的とする公的制度は、消費者裁判手続き特例法の集団訴訟、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の被害回復給付金支給制度、振り込め詐欺救済法などがある。が、迅速性に欠ける面や回復の限度、監督官庁がない隙間事案への対策の不十分さが指摘される。
このため「研究会」では、業法規制が存在しなかったり、破綻寸前といった理由で消費者被害を生じるケースを類型化し、有効な被害対策のあり方を整理・分析。被害の早期防止を図ることができる実効性の高い手法を検討してきた。
具体的手法の候補は、行政単独ではなく裁判所も関与する仕組みが有効と考えられることを念頭に、消費者庁が裁判所に対して緊急差止め命令を申立てることができる制度が上げられていた。
11年前に報告書
23年に自民が提言
2011年に報告書がまとめられた「財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム」は、不当利得隠匿を防ぐため消費者庁に破産手続き開始の申立て権を付与することを提案。これを引き継ぐ形で発足した「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」は、13年の報告書で、やはり申立て制度に言及。差止めや財産の保全、違法収益の吐き出しを裁判所が命じることを申し立てる制度を提案していた。
しかしその後、庁内で具体的に検討されることはなく“棚ざらし”状態に。11年を経過した昨年、「研究会」の議題に浮上した。「研究会」は、有効策を検討する際に踏まえるデータの一つに13年の報告書を含めている。
「研究会」における議題化にも伏線がある。
23年12月、自民の消費者問題調査会が消費者庁長官に提出した、消費者法制度のパラダイムシフト推進等を求める提言書の中で「悪質かつ深刻な消費者被害が急速に拡大する場面に厳格に対応するためには、例えば、裁判所を介した手続の活用も含めた実効性の高い手段等が考えられる」と提言されたことだ。