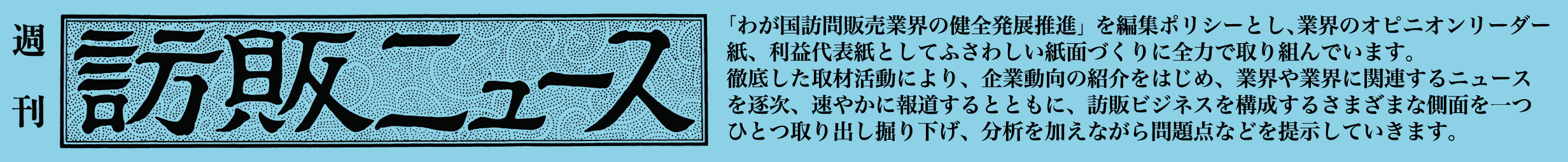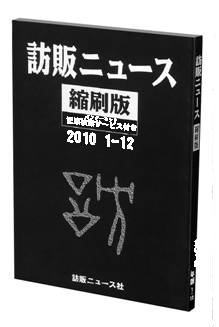政界再編と消費者行政の行方
消費者問題特別委でも「過半数割れ」
野党が与党を上回る、委員長に維新
10月27日投開票の衆院選で、連立政権を組む自公が過半数割れを起こしたことにより始まった政界再編。この波が、消費者問題を総合的に議論し、対応策を講じる特別委員会にも及んでいる。野党の委員数が与党を上回り、委員長には野党議員が就任。特定商取引法をはじめとする消費者関連法は、与党の賛成多数で政府案がそのまま委員会を通過し、本会議で可決・成立してきた。野党の異議は附帯決議として反映されるにとどまってきたが、この構図に変化を生じる可能性が出てきた。
野党にベテラン勢
11月14日時点の所属委員数は35委員。内訳は、自公の与党が計17委員で、これに対して野党の立憲・維新・国民民主・共産・れいわの5党は計18委員。野党が過半数を占める。
委員の動議で選出されるケースが大半の委員長は、維新の浦野靖人議員が就任。過半数を占める野党の意向が通る形となった。
計7人の理事は、与党から2委員、野党から5委員が就任。全委員における与野党の人数差は1人だが、理事の人数差は3人となっている。
野党の理事は、消費者問題に長く取り組んでいる複数の「ベテラン勢」が務める点も注目される。
立憲の大西健介委員は、16年の国会で、政府主導の国民生活センター移転構想を問題視する観点から質問趣意書を提出。
同じ立憲の尾辻かな子委員は、特商法改正案が審議された21年の国会で、電磁的方法によるクーリング・オフでも発信主義が維持されるように条文を修正させた。